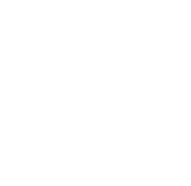ABOUT ME
Salliee Fukushima
「決めつけ」を葬り、「思い込むチカラ」を得ること 。
中学生のある日、剣道場で創作ダンスの授業をしている最中でした。私は20名程のクラスメイトに囲まれ、踊るように言われたことがあります。クラシックバレエを長年習っていた私は、きちんと振付を覚えていましたので、逃げ場のないその状況で、心の痛みに耐えながら踊ったのを思い出します。
それまでずっと我慢し続けていた「意地悪に耐える」日々に、“強がって”毎日学校へ通っていた心は張り裂け、とうとう我慢ができなくなってしまいました。そして、泣きながら母に訴えました。
「学校に行きたくない!」
自分が愛されないその場所へ、なぜ、毎日自らの歩みを進め、1日の大半を過ごさねばならないのかと途方に暮れ、振り絞った…一言でした。
そんな私に母は─
「ああ、よかった♡」と、言いました。
この言葉だけを切り取れば、疑問に思う方もいるかもしれません。だって、傷ついた我が子の姿を見て「よかった」と思う親などいないでしょう。むしろ、親としては許しがたいことであるはずです。
どんな親でも、目の前で傷ついている我が子に胸が痛まないわけがありません。それは、私自身も“人の親”として簡単に想像がつくことです。しかし、その時の母は、誰を咎めるわけでもなければ、私の感情に流されるわけでもなく、私の心だけを真っすぐに見つめ「あなたが“心が痛い”という痛みのわかる、優しい子でよかった。」と、言ったのです。
もし、私が当時の母ならば、傷つく我が子の姿にとても耐えられないし、娘の代わりに殴り込みに行っているとすら思うほどです。しかし、感情が激しく揺さぶられる時にこそグッとこらえ、真っ先に私の心の優しさを褒め、温かく包んでくれた母。
何か予期せぬことで傷つくとき、人や物、環境のせいにして、ソレを咎めたり、文句を言ったりするのは簡単です。しかし、この時の母の言動・行動のように、自分の感情云々よりも、“なぜソレが起きたのか”という「出来事」の一歩先を考え、学びに変えてしまう方が、文句を言ってブスにならずに済むし、「嫌だ」とか「辛い」などの負の気持ちに執着しなくていいので、心が楽だということに気づきました。
本当の優しさとは、偽善ではない愛のこと。
きっとあの時、母が私に向き合うことを後回しにし、怒って、学校に乗り込んでいたなら、私はこんなに深く愛されていることを、心の底から味わうことはなかったと思います。
傷ついてもなお、意地悪した相手を“ともだち”と表現する私の心の優しさを見つけ、認め、褒め、誰だって、遅かれ早かれ“心が”傷つくときが来る。その痛みを味わうタイミングが、わたしが“たまたま”早かっただけであり、この痛みを早い時期に知ることができたのは、今後の人生においてラッキーなことなの“だろう”と漠然と理解したのでした。
母の言葉で我に返った私は、すっかり気持ちが落ち着き、冷静になる事ができました。
現在も、社会問題として根深く、なかなか無くならない「いじめ」。これは、人間に“意地悪してやろう”という気持ちがある限り、無くなるわけがないものです。重要なのは、それをどう実経験として糧に変えるかではないでしょうか。この“糧に変える”ことは、意識すれば可能であり、糧に変わると、その経験は「生きる力」というポジティブに生まれ変わります。
その時から私は、過去に囚われて生きることやネガティブな気持ちに執着することを辞め、「すべてのことに意味があり、経験して損する無駄などひとつもない」と考えるようになりました。そうすれば、善悪関係なく、経験はすべて糧であり感謝に値する心の財産です。
このことは、自身の子育て観にも大いに影響を与えています。人はたとえ“意図していなくても”他人を傷つけてしまうことがあり、また、他人の言葉で自身が傷つくこともあります。それは人として生きる上でとても自然なことであり、倫理観や道徳観を形成するうえでは寧ろ「必要な経験」であると言っても過言ではなと思います。ただ、だからといって“意図的に”傷つけることは許されないことですよ。
母が教えてくれた大切なことに気づくまでは、自分に向けられる様々な意地悪に対していちいち傷つき、悲しみや辛さに執着し、思い悩み、自分のことを嫌う人に対して「どうすれば好かれるのか」や「なぜ嫌われているのか」ばかりを考え、実際に「私の何が嫌で、どうしてほしいのか」と質問したこともありました。しかし、そこにはいつも答えはなく、意地悪はなくならな
かったのです。
いくら、”汚いものを知らなければ、美しさの本当の意味は分からない“と頭で分かっていても、たかが13年間しか生きたことのない私の経験値では、到底乗り越えることのできない大きな壁に押し潰されてしまいそうな日が多くありました。
何度思ったかわかりません。でも、いつも家族の顔が思い浮かび、思い留まるわけです。そんな中、ある事実と出会いました。
「日本自殺率世界トップ(いつも上位)」
これを知ったとき、率直に「この国は病んでいる」「大人になりたくない」「でも、このまま子どもであることも嫌だ」と思いました。自殺問題は、現在もなお目を背けてはならない現実です。私は37歳でこの本を書いていますので、20年以上も前から、ずっとこの現実は続いているということになります。
子どもながらに、意地悪に耐えながら苦しむ日々が、大人になっても続くのではないかとゾッとしました。“病んでいる”という失望感は、未来への希望を奪い、世の中の“生き難さ”のようなものを感じさせ、“このままでは、意地悪に殺される”という恐怖心や危機感へと変わっていきました。
2021年の今日も、アフリカ大陸の平均年齢は20歳前後。私たちは、明日なんて誰にも保障されていないのに、明日が来ることがさも当然のように錯覚しています。自分一人で生まれてきたわけではないのに、「自殺」という、両親の大切な存在を殺そうと考えてしまったことを反省し、どうせなら「生まれ変わっても“もう一度生きたい”!と思えるような生きかたがしたい」と考えるようになりました。
“最後は結局死ぬのだから”
そう考えると、後悔しない人生を歩むために、単身アメリカへ渡ることを決意しました。14歳の冬でした。
インターネットやスマートフォンなどない時代。情報を得るためには自分で発言し、行動を起こすしかありません。
「アメリカに行きたい」
私の言葉に、母は─
「自分で飛行機のチケットとパスポートを取ってきたら、行かせてあげる。」
一瞬、突き放されたような感じがする言葉ですが、私は本気であることを証明するため、すぐに行動に移しました。
勇気を振り絞って、旅行会社へ。ニューヨークへ行く方法、チケットの金額、チケットの他に何が必要かなどを教えてもらいました。そして、パスポートも多くの大人の手を借りて、無事に取得することができました。結果、私が「自分の意志で決めたこと」に対し、「行動を伴って見せた」ことによって「本気」が伝わり、母は快くサポートしてくれました。
出発の直前。マッサージ機の上で寛ぐ父に言いました。「アメリカへ行くから、空港へ送ってください。」父にとっては、正に青天の霹靂!怒りにも似たような、驚いた顔で─
「何ばいいよっとかお前は(何を言っているんだお前は)!!」
これまで、命に代えても大切に守ってくれた父の元を離れることは、私にとっても只ならぬ決断でした。そんな大好きな存在から遠く離れ、私は本当にやっていけるのだろうか…そんなことも頭に過ったわけです。それでも、これ以上日本で生きることは難しかったので、“反対するであろう”父には黙って渡米の準備を整え、あえて後戻りできない状況を作ったのでした。
私には「心休まる家族がいる」「いつでも帰れる場所がある」「いかなる私も愛してくれる家族がいる」。だからこそ、安心して背を向け、飛行機に乗り込むことができました。「英語なんて分からない。でも、現地に行けば、きっと分かる日が来るに違いない。英語ってイギリス語でしょ?アメリカ人が喋れるんだから、私にできないわけがない!」そう、思い込むことにしたのです。
家族以外には何も告げず、たったひとりで乗る飛行機。そう簡単には家族に頼ることができない世界への旅立ちは、不安より、私のことを知る人がひとりも居ない場所で、新しいスタートを切れることへの期待感の方が大きかったです。それに、意地悪からの脱却という意味では、どこか気分がスッキリとして前向きであったと思います。
鹿児島から羽田空港へ。羽田からバスで成田空港へ。成田からニューヨークのジョン・F・ケ
ネディ空港へと歩みを進めていくのですが、最後の機内で私の価値観を一瞬で凌駕する衝撃的な出会いがありました。
ニューヨークまでの13時間。英語なんて、A~Zまで書けるか書けないか程度のレベルであった私の隣には、若いアメリカ人女性が座っていました。私たちは、カタコトの英語と日本語でおしゃべりをしながら過ごし、目的に到着。飛行機から降りた彼女は、空港へ迎えに来ていたご家族に向かって、言いました。
私は、とても驚き、同時に心がスカッと晴れた感じがしました。ほんの13時間前まで、日本であんなに思い悩んでいた嫌われ者の私が、“まったく同じ人”なのに、誰かの「ともだち」となっていたのです。「どうすれば好かれるのか」という疑問の答えは、「ありのままでいい(自分を変える必要はない)」ということに気づくことができ、たった一言でこれまでの価値観が凌駕されました。そして、人種のるつぼで、そもそも多様性に寛容なアメリカを心地よく感じ、その後大学生になるまで留学は続きます。
大人になって振り返ると、“嫌われる理由”を考えている時点で、私自身が、自分を他人の物差しに当てはめ、“最低な人間だから嫌われるんだ”とジャッジしていたように思います。“ありのままで愛される喜び”を体験させてくれた彼女のおかげで、傷ついた心により沁みた温かさがあり、”汚いものを知らなければ美しさの本当の意味は分からない“ということが腑に落ちた感じがしました。
ニューヨークでの生活は、ひとり、時が止まったかのような気分でした。無数の電光掲示板から流れる大音量の音声、空に突き刺さる高い建物に、生き急ぐかのように早歩きの人たち。雑音にしか聞こえない「英語」、空が見えない息苦しさや圧迫感など、田舎っぺの私には追い付けないスピード感の都会の真ん中で雑踏に紛れ、何度も立ち止まっては、ボーっとしてしまったのを覚えています。
当時、クラシックバレエを習っていたこともあり、幼いころから芸術鑑賞がとても好きだった私は、ブロードウェイでありとあらゆるミュージカルやバレエを鑑賞しました。気の赴くままに行動し、英語しか聞こえない世界で過ごしていると、だんだんと耳が慣れてくることがわかりました。
まるで生まれたての子どものように、最初は何か言われるだけだった私が、場面をセットで言葉を聴くことにより、「真似て喋る」ことへチャレンジできるように。それがやがて、「会話」へ
と発展し、今となってはある程度流暢に喋れるようになりました。
「言葉の壁」など、一見ネガティブに感じることも、「この出来事は私に必要な学びを与えてくれる」という意識さえあれば、挑む勇気が生まれ、以前なら思い悩むのに使っていた時間を、建設的な答えを導き出すための時間として使え、最良の答えとの出会いや自分自身のレベルアップに繋げることができます。
歩みを進めようとするとき、「無理」「できない」と決めつけて、自身のポテンシャルに蓋をすることや“やらない理由”を沢山並べて「しない」のは簡単です。しかし、「できる・できない」を軸に判断してしまう自動思考を葬り、「やる・やらない」を軸に判断する方が、心に自然と従えるようになりました。自分自身を決めつけず、ネガティブな感情に執着せず、何でも「できる!なるようになる!」と思い込んで挑戦し続けています。
フィールドを住み替える
ヤンキーの友達は、ヤンキー!だから、社長の友達は社長が多いに違いない!と考えたのが、表題の発端です。
Facebookの過去を辿る機能によって、当時の投稿が出てくることがあるのですが、私が本格的に「社長になる」と決めたのは、19歳の頃です。当時、「英会話のできる人」という求人に応募し、見事合格。しかし、日本の社会は年功序列。個人が持っているスキルより以前に見た目が9割。人は皆違っていて、ひとりひとりが“自分にないもの”を持っているわけなので、私は誰に対しても敬意をもって接する方ですが、私の“英語ができる”というコンテンツに対して「年下だから」「新人だから」というだけの理由で軽視される組織の在り方や風潮がとても苦手でした。だから、「こんな人の言うこと聞きたくない!」と思って、「社長」の道を選んだ次第です。
社長になると決めたからには、反面教師。“何屋さん”になりたいわけでもないのに、社名や理念を早々に掲げ、自分の思い描く理想の組織像について想いを膨らませていきました。
そして、まず、本を読むのをやめました。
元々弁がたつ方である私は、受け売りで他人の言葉を語るのがうまいのです。そして、そういう自分が薄っぺらくって嫌いでした。だから、本ではなく、気になる人には実際に会って、話を聞いてみようと考えたのです。色んな会社のトップとの出会いの中で、自分の思い描く組織像に近づき、仲間を得るヒントを見つけることができました。多くの打席に立ち、経験を積み重ね、それでこそ得られる言葉の奥行きがあることにも気づくことができました。
次に、断捨離です。特に、気持ちの執着を断つことでした。
人は弱いから、自分のネガティブな気持ちにどうしても執着してしまいます。かつては、私もそうでした。でも、意地悪から脱却するために渡米したとき、母によって気づかされたように、不要な感情やネガティブから気持ちを「断つ」ことで自分自身が救われるということを、私の心はよく知っています。また、物理的に使わないものを「捨てる」こと、自分にとってポジティブな影響がない人から「離れる」ことなど、「断捨離」の本意を真剣に考え、愚直に実行しました。
そして、最後に「フィールドを住み替える」ことです。
例えば、冒頭に書いた通り「社長の友達=社長」だとしたら、“社長になりたいから、社長のお友達を作ろう!”と考えたのです。そして、若気の至りか、私はどんどん突き進みます。
私が選んだ社長友達を作る最速の方法は「高級クラブで働く」ことでした。それは、それなりの金額を支払うことのできる社会的地位の高い人たちが集まる場所。接客のために毎日新聞を読んでは勉強し、品位ある社交場のひとりとして立ち振る舞い、結果的に素晴らしい出会いや経験を得ることができました。その後は、熊本の企業や佐賀県で会社員や個人事業主をしながら、更に多くの経営者と知り合うことができました。
彼らは、“まだ社長ではない”私をとてもよく可愛がってくれました。そのうえ、仲間との集まりに呼んで下さり、経営のノウハウや失敗からの学びなど、人様がお金を出して聞きに来るようなお話を直に聞くことができました。
Achievements
my AWARDS

National Award
Commonwealth Writers Prize
july 2015

International Award
Winifred Holtby Memorial Prize
august 2016